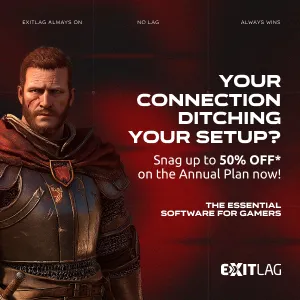あるトランドール亡命者の記録
私は物書きではない。だが私が見たことについて、誰かに伝える必要があると思い、ペンを握った。恐ろしいあの日の真実について。
本来、ライカンたちは凶暴で残忍だが、子どもや戦士でない女性には手をださないという伝説がある。ハンターは残忍に殺されたが、女子どもは無事に村に戻って来たという話があるからだ。
しかしあの日は違った。私はアーキウム軍団と手を握った領主の名で、トランドールまで進出したライカン・コーワンズーキ族を討伐しに出かけた。コーワンズーキとは部族の名前でもあったが、代々伝わる連中の族長の名前でもある。もしかしたらそれ自体が名前ではなく、一種の称号みたいなものなのかもしれない。当時コーワンズーキ族は恐ろしい勢いで、討伐戦を行うとこちらが返り討ちに遭うのではと恐れていた。聞いたところでは、新しいコーワンズーキは少し前に族長となり、ものすごい力を持っているとのことだった。だからトランドールまで進出できたんだろう。
コーワンズーキの大きな咆哮を聞いた時、私はその場にうずくまらずにいるので精一杯だった。森から急に現れたライカンたちは仲間たちを殺し、そばにいた仲間が真っ二つになった瞬間、私は必死で木に登った。その後、下に見えるのは悲鳴と死だけだった。
恐怖で震えあがり、必死で木の枝にしがみついていたのだが、急に何かが焼けるニオイがした。まさかライカンたちを殺すために森ごと燃やすつもりなのかと急に怖くなった。しかし木から下りたら最後、ライカンの爪の餌食になると思い、私は下を見下ろすばかりだった。
その時私の目に移ったのはあの少女だった。十四、五?真っ黒な服に、真っ黒な髪がうねっていて現実離れしていた。彼女の周囲を回っていた紫色のオーラは、その光景をさらに夢のように思わせた。
その次に見た光景は、死ぬまで忘れられない。
少女が軽く手を振ると、彼女の周辺にあった紫色のオーラのような光が燃え上がり、周囲にいたライカンたちは灰になった。そう、文字通り灰となったのだ。全身が灰に代わり、空中に飛ばされて行く様に、私は声を出すこともできずに凍り付いた。少女が歩く道には燃える臭いが漂った。
彼女の後ろ姿から目を放せずにいると、前の方から他のライカンたちよりも頭一つ分大きな恐ろしいライカンが現れた。変わった毛皮を被っていることから、私は奴こそがコーワンズーキであると推測した。彼女はゆっくりとコーワンズーキに向かって歩いて行った。
信じられるだろうか?あの巨大なコーワンズーキに向かって少女が手を上げると、コーワンズーキはそばにいた部下を前に投げた。コーワンズーキの代わりに前に出された部下は次の瞬間灰となっていた。少女は踊るかのように身軽にもう一度手を振った。コーワンズーキの巨大な身体がすごいスピードで、ぼうっと立っていた部下たちの後ろへと消え、彼のそばにいたライカンはまたしても灰になった。
かの悪名高く、誇り高いことで知られていたコーワンズーキは、自分が助かるために部下を次々に犠牲にした。すぐに少女が軽く指をはじくと、コーワンズーキのとてつもない悲鳴が響き渡った。私はその声に驚いて木から落ちそうになったがなんとか耐え、コーワンズーキは巨大な図体に似合わぬ素早い動きで逃げて行った。
後で聞いたのだが、あの時コーワンズーキの目が一つなくなったそうだ。とにかくそうしてコーワンズーキは腹心を失って逃走し、その後のことは私も覚えていない。後で目を覚ますと、あのまま気絶して木から落ちたそうだ。幸いあの少女は私のような一兵卒には興味がなかったのか、あるいは味方だったのかわからないが、手足が一本折れただけで済んだ。頭を打たなかったのは本当に幸いだった。
しかし目を覚ました私は、到底居ても立っても居られなかった。灰となって消えたライカンたちの姿は夢にも現れた。いつ彼女が周りの兵士たちを灰にして、死の女神のごとき姿で消えてもおかしくないと思った。
結局私は手足の負傷を言い訳に、なんとかして森の境界にあるキャンプに残り、死を覚悟して脱走した。ほとんど這うようにしてストーンガルドの方へと渡り、村を見つけた時、ブルブルと震えていた私はその時ようやく滝のような汗と涙を流した。村の人々は私が脱走兵であることを知って、温かく迎えてくれた。彼らの話では、北のトランドールへ領土を拡大していたコーワンズーキ族は、ある時急に戻って来ると北へと続く橋をすべて落とし、渓谷に閉じこもったそうだ。また、それ以降ライカンたちは女子どもも関係なしに殺すようになったという。
村の人々はトランドールもストーンガルドもそう変わらないと言って私を慰めてくれたが…私は気にしていなかった。ただあの恐ろしい少女と同じ土地にいないだけで満足だった。
誰かこれを読んでいる人がいるなら、頼みたいことがある。紫の光をまとわせた黒髪の少女が現れたら…いや、今はもう少女ではないかもしれないが…どうか逃げてくれ。そこがどこだろうと、どこに所属していようと、逃げるんだ。きっとそれだけが生き残る唯一の道だろうから。