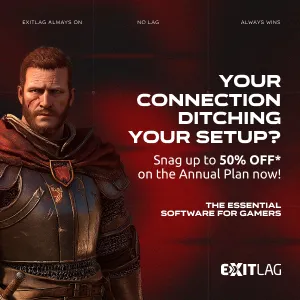白角のハーメルと狼の王イスケール(1)
フリン・レクストーン著
キャスラータウン広場の片隅で所在なさげに立っている少女を見かけたことがあるだろうか?その愛らしい少女はまるで助けを待っているかのように立っているが、近づいてみると急にキリッとした冷徹な目になり、近づいてきた人への評価を口にすると、それっきり黙り込んでしまうという。何人もの人が体験していることであるが、私もまた軽い気持ちで少女に近づき、困惑させられた一人だ。しかし私は、彼女が何に困っているのかを知りたい一心で、彼女のそばで何時間も粘っていた。やがて彼女は、ため息をつきながら私に話しかけてきた。
「お気遣いはありがたいですけど、おじさんはとても弱そうなんですもの」
これは何たる言い草だろう。私は物書きを生業とする旅人でしかない。弱そうだと言われたからといって怒る理由はないはずだ。
「君の事情を聞くには、耳が二つあれば十分じゃないかな?君を助けられる人を私が見つけられるかもしれないだろう?」私がそう言うと、少女は納得したらしく目に生気を宿らせ、このように語った。
キャスラータウンのすぐ北にあるブラックハウル平原は、古くから多くのシカとオオカミが生息する豊かな平原だ。オオカミは主にキャスラー修道院が建っている低い山を中心とする草原地帯と洞窟に棲み、シカは平原の中心にある湖の北の広い草原を棲み処としていた。ヒューマンが滅多に訪れない環境において、それらは自然にバランスを取って生きていた。
白角のハーメルと狼の王イスケール(2)
そのようなシカの中に、白い角を持つ大きなシカがいた。巨大と称するほかないシカで、目撃したハンターの証言によれば、その角はまるでトランドールの黒い森のように高くそびえ、その目には熟練のハンターをも凌ぐほどの聡明さが宿っていたという。肩が他のシカの頭の高さにあるほどの巨体だったこのシカのことを、ハンターたちは敬意を込めて深い川の水を意味(ハンターの間では聡明さを意味する名前でもあるという)するハーメルという名で呼んでいた。ハーメルが率いるシカは狩るのが難しく、ラスランのハンターの間では、ハーメルが姿を見せた日は狩りを諦めるべきとすら言われていた。そうした事情はシカを食料とするオオカミたちにも影響を及ぼし、それが原因で起きた事件の中に、狼の王と呼ばれたイスケールとの戦いがあった。
イスケールというのは「グレイファング」という意味を持つ名だが、黒オオカミの中でもとりわけ体が大きく凶暴なため、ハンターの間でも名が知れているやつだった。ハーメルに従うシカの群れが平原を牛耳っていた頃、イスケールはブラックハウル平原のオオカミの群れを支配下に置き、堂々とハーメルに挑戦した。何人かのハンターの目撃談によれば、その戦いは丸二日間続き、結果はイスケールの惨敗だったという。
オオカミたちのボスだったイスケールが敗れると、もはや平原にはハーメルの群れに挑める者はいなかった。傷つき、プライドを踏みにじられたイスケールは、群れの一部を連れてブラックハウル平原を去ってしまった。人々の間ではハーメルの伝説がさらに広がり、そうして平原は平和になったかのように思われた。
白角のハーメルと狼の王イスケール(3)
驚くべきは、天敵が消えてもシカの数が極端に増えることはなかったという点だ。人々はシカの増加により平原が荒れ果てることを懸念したが、むしろ小動物の数が増え、平原は人々が余暇に訪れることができる楽園のような場所となった。一部のハンターは、これすらもハーメルの賢明さのおかげだと言い、ハーメルをまるで山の神か何かのように崇拝し始めた。
それから10年近くの間、ラスランのブラックハウル平原は危険な猛獣が存在しない動物の楽園となり、人々はこの場所の名をハーメル平原に改名しようと言い出した。しかし、あらゆる平和には終わりがあり、楽園はいずれ崩壊するもの。10年間続いたハーメルの楽園も、とある事件によって幕を閉じることとなった。
「大人たちはみ~んな覚えてるんですって」
少女は怖がらせるかのように、大きな瞳をクルクルさせながら語った。
このこましゃくれた少女は意外にも語り手としての才能に富んでいたので、私はハチミツキャンディー2つとバターライ麦クッキー5つを捧げても惜しいとは思わなかった。
ハンターたちの記憶によると、その事件はブラックハウル平原からイスケールの群れが去ってからおよそ10年後に起きたという。ある日、突然おびただしい数のオオカミがラスラン北部に姿を現し、連中はあっという間にブラックハウル平原を掌握した。いつものようにピクニックに訪れた人々がオオカミに出くわして逃げてきたという話や、オオカミがハンターを襲ったという話が村の広場を駆け巡った。そんなある日、レジスタンス監視塔から見ることができる大きな岩の上に、誰もが知っている大きなシカの死体が晒された。巨大な角、他のシカの倍ほどの巨躯。それは紛れもなくハーメルの死体だった。
人々、特にハンターたちはそれを聞いても信じることができなかった。しかし、レジスタンスが回収した死体を何人かの老いたハンターが本物だと確認してからは、事実を否定する者はいなくなった。人々は恐怖に震え、平原に向かうことを禁じた。
白角のハーメルと狼の王イスケール(4)
ハンターすらもブラックハウル平原から村に逃げ帰ってきた。そんなハンターのうち何人かは、オオカミの群れの先頭に、紫色の瞳を輝かせ、恐ろしい灰色の牙をむき出しにしている巨大なオオカミがいたと語った。ベテランハンターたちは耳を疑った。イスケールが帰ってきたというのか?10年も経った今さら?しかし、恐怖に陥った人々に事実を確かめる余裕はなかった。オオカミたちはブラックハウル平原を掌握しただけでは飽き足らず、レジスタンスに対応する暇を与えぬまま、大勢で黄金のライ麦畑に押し寄せた。人々は悲鳴を上げながらキャスラータウンに逃げ込み、逃げきれなかった人々は修道院に避難した。
村中の人々が怯えて身を潜めていたそのとき、かえって修道院から飛び出した者がいた。領主ホブスの息子であるヘンリー・キャスラーだった。
ヘンリーはホブスの一人息子で、幼い頃から病弱なせいで父である領主を心配させていた。しかし、幼少期から村の子供たちと分け隔てなく付き合っていたヘンリーは、成長するにつれ、自らも父や叔父のようにラスランを守る立派な大人になりたいと夢見るようになった。やっと少年らしさが抜けてきた10代のヘンリーにとって、あの日はまさにその夢を叶える日だったのかもしれない。
そんな話を面白おかしく語っていた少女の目元に涙が光った。
「あのときヘンリー様が来てくださらなかったら、私は修道院で死んでしまっていたと思います」
それから語られたのはとても信じ難い話だったが、少女は他にも何人かの大人が証言してくれるだろうと主張した。おそらく嘘ではないのだろう。いくらか誇張はあるのかもしれないが、10代の少年だったヘンリー・キャスラーが修道院に火を放ち、そうすることで怪物となって帰ってきたイスケールをあの世へ送ったという事実は決して揺るがないのだから。
白角のハーメルと狼の王イスケール(5)
少女の語るところによれば、ヘンリーは勇ましく剣を振るってオオカミを倒しただけでなく、子供たち全員を村に送り届けた後、イスケールを倒すべく再び修道院に戻ったのだという。
結果として、オオカミの大襲撃は修道院を最後に止まり、ボスを失ったオオカミの群れはブラックハウル平原へと帰っていった。ハーメルという傑出したボスを失ったシカもまた平凡なシカの群れに戻ったが、妙なところが一つあった。ブラックハウル平原のシカは、自らの死を悟るとハーメルの死体が置かれていた岩に向かい、群れを離れて最期を迎えるという。ハンターたちはその場所をハーメルの墓と呼び、ハーメルの魂が残っていてまだシカを守っているのではないかと語っている。
「そして、毎年ヘンリーを偲ぶために何かを行っていると…」
「はい!だから今年は絶対、オオカミ狩り大会の証を手に入れてみせます!」
なるほど、それは確かに弱い者にはできない頼み事だった。しかしこの少女なら、何とかして頼み事を聞いてくれる勇者を見つけられそうな気がした。ラスランのブラックハウル平原で行われるオオカミ狩り大会に、このような由来があったということを記せるようになっただけでも、お菓子を捧げた価値はあったというものだろう。この少女が今年の大会に間に合うことを祈ろう。ラスランの小さな英雄を称えるためにも。